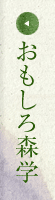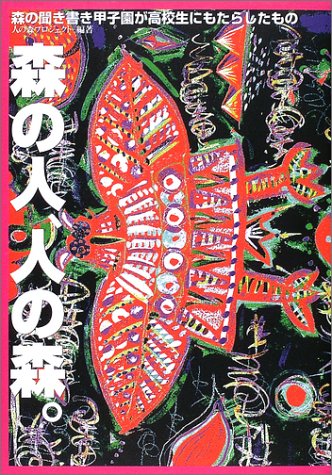体験しました!狩猟女子のやさしいボディーブロー
日々私たちの食卓にのぼる肉。例えばスーパーでパック詰めになっている鶏もも肉は、誰かがどこかで、生きている「ニワトリ」から「お肉」へと変容させる「仕事」をした結果。でも、都市で暮らしていると、そういう全貌が見えにくくなりがちです。
この本の著者、畠山千春さんは、都会暮らしの20代女子でしたが、3.11をきっかけに「何か大きなもの」に依存した暮らしから一歩進みたい!と思い、「食べものを自分でなんとかする」ことを決意。多くの人がお米や野菜づくりに向かう一方で、彼女の目は「お肉」に向かいます。

生まれて初めて鶏を絞める前日には、「命をいただくってどういうことなんだろう?」と眠れぬ夜を過ごし、いよいよ絞める時には手を合わせて「ありがとう」「ごめんなさい」と祈るような気持ちになる。そして、「ああ、もう鶏肉は食べられないかも……」と思いながらも、毛をむしったあたりから「あれ、美味しそう」と感じる。そして、その肉や内臓やトサカまで余すところなく、有り難くいただき、「さっきの鶏が自分の一部になった」、命をいただくってこういうことなのかもと納得する。そんな命と向き合う葛藤やヒトという生き物としての感覚、一人の女子としての迷いや苦しみと奮闘ぶりを、容赦なく生々しく、でも優しく、伝えてくれています。
初めて鶏を絞めてから約1年半。著者は「動物も自分も一対一の命」、自分が一動物であることをもっと感じたいと狩猟免許を取得し、さらに命と向き合うことを深く追い求めて行きます。その描写は、読みながら時に手に汗にぎり、ギョッとし、涙を誘われ、拍手を贈りたくなり……。

イノシシとの闘いから肉が美味しそうな料理になるまでは、美しい写真で。解体から「皮なめし」の方法などはイラストで詳細に解説されています。また、解体&狩猟が見学・体験できる場の情報や、野生肉料理のレシピまで、「やってみようかな」という人にとっては至れり尽くせりの入門ガイドになるでしょう。
自分が口にする肉と、生き物の命。頭では理解しているつもりの「命のつながり」を、ずどんと身体で感じさせてくれる一冊です。
(編集部:おおわだ)