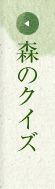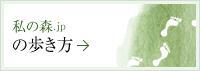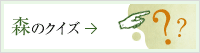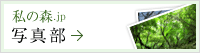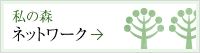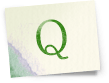
3メダカ

メダカは10℃を下回ると冬眠しますが、高温には比較的強く、
一般的に夏眠することはないとされています。
「冬眠」に比べて「夏眠」とはあまり耳慣れない言葉ですが、どちらも生物の「休眠」という現象で、生きものたちが、ある一定期間活動や成長を中断・休止させて生命を維持することを言います。この内、暑さや乾燥などに耐えるために行われるのが夏眠です。
熱帯地域に生息するワニやカエル、ハイギョなどは、高温乾燥の夏季に水分蒸発を防ぐため、湿度の高い洞窟や地中に潜って夏眠します。古代魚と言われるハイギョ(肺魚)はエラと肺の両方で呼吸する魚で、水の干上がる乾季には泥の中に入って自身の周りに粘液の「繭」をつくり、そこで数ヶ月から数年もの間、全く水を飲まずに生きることができるそうです。「夏眠」と名付けられていますが、実際は夏という季節に限られたことではないようです。
日本でも、カタツムリやテントウムシ、ヒキガエル、トカゲ、カナヘビ、イカナゴ、ヒガンバナやフクジュソウをはじめ、さまざまな生物が夏眠することが確認されています。
たとえば、皮膚から水分を吸収しているヒキガエルは、涼しい土中に潜って夏眠し、目覚めると今度は冬眠に向けての捕食活動に入ります。ナナホシテントウは、気温が27℃以上になって餌となるアブラムシが減ってくると、樹皮の間や草陰・葉の裏に隠れて休眠。カタツムリは「エピフラム」と呼ばれる粘液を固めた物質で殻の開口部を覆い、殻の中に体をしまって乾燥から身を守り、葉の裏や木の枝にくっついて雨を待ちます。また、ヒガンバナは、他の植物が葉を茂らす初夏になると地上部を枯らして根だけで生存し、秋の開花まで休眠します。
こうしてみると、休眠は、厳しい時期を生き抜くための生き物たちの生存戦略といえそうです。温暖化が進む今、生きものたちの冬眠の期間が短くなったり、冬眠しなくなったりする例が報告されています。その一方で、夏眠はヒトにも必要なのではないか、そんな生体機能を備えていればいいのにと思わずにはいられません。異常気象を生き抜くために…。
参考リンク
ゲスト出題者募集!
編集部では、面白いクイズ出してくださる出題者を募集しています。
私の森.jpの編集活動にご協力いただける、素敵なみなさまからのご連絡をおまちしております。