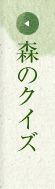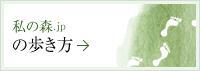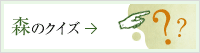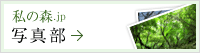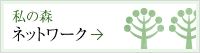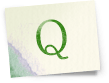
4夜にしか活動しない

スズメガの仲間であるオオスカシバ。幼虫は、他種にとっては有毒な場合もあるクチナシやコーヒーノキの葉を食草とし、成虫は、夜行性でなく昼行性で夏から秋の日中によく活動します。ビジュアルも個性的で、スズメガ科の多くが暗い色なのに対し、透明な翅(はね)をもち、背中側は黄緑色で赤の帯があり、腹部は白に黒の帯と実にカラフル。尻尾のような謎の毛束もあります。
翅が透明になるのは成虫になって直後のこと。さなぎの殻から出て羽ばたくとすぐに、灰白色の鱗粉が脱落するのだそうです。

オオスカシバの翅の麟紛(羽化後)
成虫はクチナシ、ツツジ、アザミなどの花の蜜を吸います。空中でホバリングしながら2cmほどの口吻で蜜を吸う姿は、まるで「ハチドリ」のように見えますが、オオスカシバは昆虫であり、鳥類ではありません。

ホバリングしながら蜜を吸う様子
こうしたユニークな生態の理由としては、花が多い時間帯に効率よく蜜を吸うために昼間活動する。その際、鳥や他の捕食者から目立ちにくくして身を守るために、光を反射しにくい透明な翅になった、などと考えられています。
2023年に発表された「オオスカシバの全ゲノム配列を決定〜染色体進化や遺伝子の違いが明らかに〜」という東工大(現、東京科学大学)の研究結果では、昼行性について「光受容タンパク質である長波長(LW)・青色(Blue)の波長を吸収するオプシン遺伝子の進化が、オオスカシバが夜行性から昼行性へ進化する鍵であった可能性が考えられる」と書かれています。詳しいことはわかりませんが、オオスカシバは進化の結果として昼行性になったようです。
その姿から、「空飛ぶエビフライ!」と愛称がついたり、「もふもふで可愛い」と手にのせたりする愛好家も少なくないようです。日本では本州以南に広く生息し、都市・住宅地でも見られる昆虫なので、出会えたらぜひ観察してみましょう!
「オオスカシバの吸蜜の40倍高速度撮影」
Creative Commons. Some Rights Reserved. Video by Phonon.b
参考リンク
北海道暮らし〜オオスカシバ 可愛いもふもふの虫の魅力徹底解析
「オオスカシバの全ゲノム配列を決定〜染色体進化や遺伝子の違いが明らかに〜」東京工業大学(現、東京科学大学)2023年9月14日プレスリリース
tenki.jp〜空飛ぶエビフライ!? 秋の日差しの中、キラめき翔ぶ不思議生物の正体は?
ゲスト出題者募集!
編集部では、面白いクイズ出してくださる出題者を募集しています。
私の森.jpの編集活動にご協力いただける、素敵なみなさまからのご連絡をおまちしております。